大学で経営学を学んでいた浅見綾香さんは、2年生の秋に中退。「学びながら働きたい」という思いから通信制大学に再入学し、ITとWebマーケティングを学びながら株式会社週休3日でマーケターとして活躍しています。SNSのショート動画を活用し、企業の採用支援に取り組む浅見さんに、週休3日で働くようになった経緯や、SNS時代の採用のあり方、若者世代のリアルな就職観について伺いました。

学びながら、働く。
週休3日で叶えた、私の再スタート
──通信制の大学に再入学を決めたのは、どのようなきっかけがあったのですか?
大学在学中、静岡大学の情報学部の学生と関わる機会があり、ITやプログラミングのスキルが社会で強く求められていることを実感しました。特に、課題を分解して考え、構造的に解決していく思考法が、これからの時代に必要なスキルだと感じたんです。
通信制大学を選んだのは、働きながらでも学び続けられる環境を作りたかったから。大学の4年間をただ拘束されるのではなく、実際に社会で経験を積みながら学びたいという思いがずっとありました。週休3日という働き方なら、通信制大学と両立できると感じました。
──株式会社週休3日とは、演劇を通じて出会ったそうですね。
趣味で演劇を続けていて、株式会社週休3日代表の永井が書いた脚本に出演させてもらったのがきっかけです(笑)。いろいろと話をする中で、週休3日という働き方に興味を持ちました。
1日増える休みを学習に充てることで、「働きながら学びたい」「学びながら社会経験を積みたい」という希望を両立できる。そんな働き方に魅力を感じ、2025年1月からインターンとして働き始め、8カ月ほどの経験を積み、現在は正社員として働いています。
──今はどのようなお仕事をされていますか?
法人顧客の採用対策を目的としたPR動画や、SNSで発信する1分ほどのショート動画の撮影、編集をしています。あわせて、Instagram、TikTok、YouTube、Xのアカウント開設や運用支援、ショート動画の内製化のサポートも担当しています。
また、弊社が運用する薬剤師の就職・転職サイト「週休3日薬剤師.com」や、そのSNS運営にも関わっています。投稿に登場するキャラクター「みかんちゃん」は、私が生成AIで作成したものなんですよ。こうした知見を活かし、企業への生成AIの導入支援や研修も行っています。

企業が選ぶから、若者が選ぶ時代へ
SNSで変わる採用の常識
──採用の現場に関わっていて、どのようなことを感じますか。
世代間のギャップの大きさを日々感じています。若い人たちの価値観や視点に立ったSNS運用やアプローチが、まだ十分にできていない企業が多い印象です。
今の若者は、アルバイトなどを通じて慢性的な人材不足を肌で感じており、「がんばれば、どこかの企業には採用されるだろう」という意識を持っています。つまり、自分たちは「企業に選ばれる側」ではなく、「企業を選ぶ側」だと考えています。
また、キャリア形成においても、1つの会社で長く働くという考え方は薄れています。最初の3〜4年を「社会経験を積むための下積み」と捉え、自分の興味や市場価値に応じて、転職を視野に入れながら柔軟に働くのが当たり前になっています。

──若者が企業を選ぶとき、どのような行動をとるのでしょうか。
若者世代は、何かを調べる際に、Googleなどのウェブ検索は使いません。利用するのはInstagramやX、TikTokなどのSNSです。先日、プライベートで大阪の動物カフェに行ったときも、来店理由を聞かれた同じ世代の4組全員が、「Instagramで見た」と答えていました。
私たち世代にとってSNSは、単なるコミュニケーションツールではなく、情報収集や意思決定のベースになっています。それは、採用活動も同じです。企業がどれだけ優れたホームページを作っても、SNSからの導線がなければ若者の目に触れることはありません。
──企業がSNSで発信するときに意識すべきことは?
何より重要なのが、若者の価値観や特性を理解したうえで運用することです。例えば、大学やアルバイトなどで忙しい若者にとって、時間は極めて貴重なリソースです。情報を効率的に得られるショート動画は、最も好まれるメディアと言えます。
多くの情報を詰め込むのではなく、伝えたいことを1〜2点に絞り、分かりやすく端的にまとめることが重要です。動画冒頭の数秒で「自分のことだ」と感じられるメッセージを入れたり、難しい言葉を避け、若者の言葉で伝えることを意識しています。
若者はトレンドに非常に敏感です。流行の音源やエフェクトを取り入れることで、親近感を持ってもらい、視聴のハードルを下げることができます。この感性は、同世代でなければ難しい部分でもあるため、同世代の社員が制作に関わることも、成功の鍵だと思います。
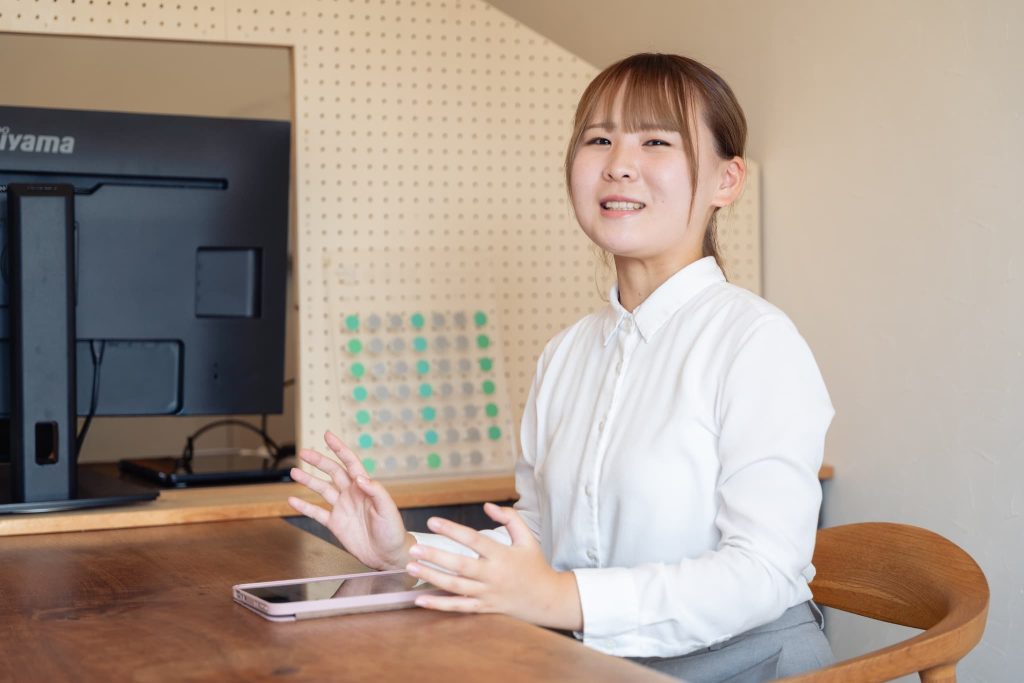
伝えるから、つながるへ──
SNSが架ける、企業と若者の橋
──SNSを活用した採用支援では、どのようなことを意識していますか。
SNSは、若い世代と企業の間に「橋を架けるツール」だと思っています。企業が採用を成功させるためには、この「橋」をしっかりと築くことが必要不可欠です。橋を架けなければ、若者との接点を自ら断ってしまうことになります。
ショート動画は、テキストや写真では伝わらない、人の表情や職場の空気を伝えられます。企業理念やビジョンは、言葉だけだと少し抽象的で伝わりにくいものです。でも、理念と働く社員の姿を同じ映像の中で見せることで、若者は「この会社は理念を実践している」「この人たちは、生き生きと働いている」と感じ取ります。これこそが共感を生む動画の力だと思います。
──印象に残っている事例はありますか。
ある工務店の採用動画で、昔ながらの「手刻み」という木材加工技術を紹介しました。社内では日常的な作業でも、若者にとっては新鮮で、魅力的に映ります。実際にその動画を見た若者から「この会社で働きたい」という問い合わせがありました。
企業の当たり前は、外の人にとっては魅力になり得ます。そうした視点の違いを見つけ、発信の形に変えることが、私の役割だと思っています。

──SNSを採用活動に活かすためのポイントを教えてください。
採用で成果を出すには、まず若者の視点に立つことです。企業が若者の感覚を理解しないまま、一方的に情報を発信しても心には届きません。そのためにも、若者の文化や言葉を理解することが大切です。実際にSNSを使ってトレンドを感じ、何が心を動かすのか、どんな表現が響くのかを理解する。動画制作や運用では、若手社員に権限を与えて参加してもらうことも効果的です。ターゲットと近い世代の感性が加わることで、よりリアルで共感を得られるコンテンツになります。
また、若者世代は、「入社後のミスマッチ」を極度に警戒しています。1日や2日の短期インターンでは、企業の表面的な部分しか見えず、実際の働き方や企業文化まで理解できません。私自身もそうでしたが、8カ月ほどの長期インターンシップを通じて、仕事内容や社風をしっかり知ることができました。長期インターンシップの導入は、企業にとっても学生に十分な情報を提供でき、ミスマッチを防ぐうえで有効な手段と言えます。
──最後に、今後の目標を教えてください。
これからは、企業の現場に直接足を運び、若い人と企業がより良い形で出会うために何が必要かを、自分の言葉で伝えていきたいと考えています。特に、SNSを活用することの重要性や効果について、実例を交え話せるようになりたいです。他にも、求人投稿の内容や表現もさらに工夫したい。SNSごとに異なる傾向やトーンを理解し、見る人の心に届くスキルを磨いていきたいですね。
9月からは通信制大学での学びも始まりました。週休3日という働き方を活かして、仕事と学業を両立させながら、自分自身も成長を続けていきたいと思います。学びと実践を行き来しながら、企業と若者の“橋渡し役”として力を発揮できるようにがんばりたいです。


